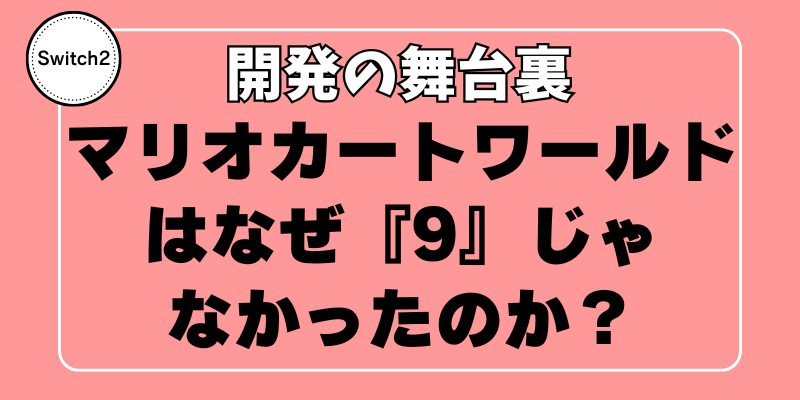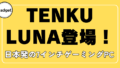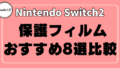「マリオカート9」はいつ出るの?
──そんな期待を裏切るように、2025年6月5日に登場したのは『マリオカート ワールド』。
なぜナンバリングを捨てて“ワールド”に?
その理由には、任天堂の「次のステージへジャンプアップしたい」という熱い想いが込められていました。
本記事では、開発者インタビューをもとに、『マリオカート ワールド』が“9”ではなかった真相に迫ります。
新しい技術で描かれた地続きの広大な世界、冒険とレースが融合する遊び方、そして「食べると着替える」革新的システム──
これまでの常識を覆すアイデアの連続は、まさに“新世代のマリオカート”と呼ぶにふさわしい内容です。
あなたが「マリオカートはもう遊び尽くした」と思っているなら、きっとこの記事で印象が変わるはず。
最新作の開発秘話を知れば、さらに深く楽しめますよ!
- なぜ『マリオカート ワールド』は“9”ではなかったのか
- フードや衣装連動など、常識をくつがえす新システムの秘密
- シームレスな世界で生まれた驚きの開発エピソード
『マリオカート ワールド』とは?|新世代マリオカートの全貌
「マリオカート ワールド」は、2025年6月5日にNintendo Switch 2と同時発売された、「マリオカート」シリーズ最新作です。
本作は、従来のシリーズのように1つ1つ独立したコースを走るのではなく、“ひとつなぎの広大な世界”を舞台にした、まさに新世代のレース体験を提供する作品となっています。
特徴的なのは、昼から夜へ、晴れから雪へと変化するリアルタイムの環境、24人同時対戦、そして「フリーランモード」による自由探索の導入です。
これまで以上に自由度が高く、プレイヤーの発想で遊び方が広がる一方、開発者たちの苦労とこだわりも尋常ではありませんでした。
本記事では、「なぜ“マリオカート9”ではなく“ワールド”なのか?」というタイトルの通り、シリーズの枠を飛び越えたこの作品の開発秘話を、任天堂公式の開発者インタビューをもとに、深掘りしていきます。
なぜ『マリオカート9』ではなく『ワールド』なのか?|開発の発想転換
「マリオカート ワールド」がナンバリングタイトル『9』ではなく、”ワールド”という名称を冠した理由は、単なるシリーズの続編ではなく、“完全なジャンプアップ”を目指した開発コンセプトにあります。
前作『マリオカート8 デラックス』で、従来型のレースゲームとしては完成形に達したという手応えがありました。
そこで任天堂の開発陣は、「新作を出すのであれば、次はどんな体験を届けるべきか?」と自問。
導き出した答えが、「個別コース」から「地続きのひとつの世界」への転換でした。
この“世界がつながる”というアイデアは、開発初期の段階から明確に設定されており、コンセプトアートには既に「MARIO KART WORLD」という文字が描かれていたとのこと。
つまり、名前からして『9』というナンバリングでは収まらない、まったく新しい挑戦を象徴するプロジェクトだったのです。
この背景を知ることで、「マリオカート ワールド」という名称に込められた開発陣の強い意志とビジョンをより深く理解できます。
地続きの広大な世界|マリオカートの概念を覆す舞台設計
『マリオカート ワールド』の最大の特徴は、これまでのシリーズとは一線を画す「地続きのひとつなぎの世界」であるという点です。
従来のマリオカートでは、レースごとに独立したコースを選択し、3周してゴールするのが基本ルールでした。
しかし今作では、各コースが世界マップの一部として接続されており、プレイヤーは時間帯や天候の移り変わる広大なフィールドを、好きなルートで自由に走り回ることができます。
この構造により、コースからコースへの移動自体もレースや探索の一部となり、シリーズ初の「サバイバルモード」や「フリーラン」など、全く新しい遊び方が実現しています。
空が赤く染まる夕暮れ時、雨がしとしと降る夜、雪山の静寂……世界の変化を体感できる設計は、もはや“レースゲーム”の枠を超えています。
この舞台設計の裏には、膨大な試作とチームの苦悩がありましたが、それを乗り越えたからこそ実現した“走る世界”。
その魅力はプレイすればするほど深まるでしょう。
なぜ『9』じゃなかった?|“ジャンプアップ”への挑戦と決断
多くのファンが疑問に感じたのが、「なぜ今作は『マリオカート9』ではなく、『マリオカート ワールド』なのか?」という点です。
この問いに対して、開発チームの矢吹プロデューサーは明確に答えています。
今作は単にコースを増やした続編ではなく、「シリーズ全体をジャンプアップさせる」意志のもと開発された“完全新作”だからです。
ナンバリングタイトルとしての『9』であれば、従来の延長線上にある新作を意味します。
しかし『ワールド』は、タイトル通り「ひとつなぎの世界で走る」というシリーズの常識を打ち破る構造を持ち、それは開発初期のコンセプトアートにも“WORLD”の名が明記されていたほど、一貫した思想に基づいています。
ナンバリングからの脱却は、任天堂が掲げる「ユーザーの想像を超える体験を提供する」という哲学の表れです。
リスクも伴う選択ではありますが、結果として「マリオカート」というブランドに新しい風を吹き込むことに成功しました。
つながる世界と地形の文脈|広大なワールド設計の秘密
『マリオカート ワールド』最大の特徴は、個別のコースがバラバラだった従来作とは異なり、すべてのコースが“ひとつなぎ”の世界に収まっていることです。
この大胆な設計を可能にしたのは、「地続き感」と「文脈のあるつながり」にこだわったレベルデザインです。
たとえば、「マリオブラザーズサーキット」からアメリカ西部のような道を経てモニュメントバレー風のランドマークが現れ、さらに大都市へと繋がっていくような構成が、まるでオープンワールドRPGのように自然で没入感の高い体験を生み出します。
開発チームは、コースの“つなぎ目”にこそ物語が生まれると考え、気候・風土・景観の変化もリアルに表現。
雪山の頂から乾燥地帯、都市部への遷移など、それぞれが意味を持ってつながるよう設計されています。
このアプローチにより、プレイヤーは“次にどんな景色が現れるのか”というワクワク感を抱きながらレースを進めることができ、マリオカートの遊びに「探検」の要素が加わりました。
BGMと音の進化|ジュークボックスと200曲超の新体験
『マリオカート ワールド』の没入感を支えるもうひとつの要素が、「音の演出」です。
今作では、BGMや効果音(SE)がこれまで以上に精緻かつダイナミックに設計されています。
サバイバルモードでは、次のコースが近づくと、BGMが自然とアウトロに入り、コース突入のタイミングで次の曲の前奏へとスムーズに切り替わります。
これにより、レース中にまるで“ライブのメドレー”のような臨場感が生まれます。
さらに、自由に世界を走れる「フリーラン」モードでは、各プレイヤーのルートやペースに応じて自動で曲が切り替わる「ジュークボックスシステム」が導入されました。
この仕組みに合わせて開発されたBGMは、なんと200曲以上。
すべてがシリーズ過去作や他マリオシリーズのアレンジで構成されており、ファンにはたまらない構成です。
生演奏で収録されたBGMは、ハーモニカやバンド編成など“わんぱく感”を感じるアレンジが多数。
走るルート、天気、時間帯によって違う音楽が流れるという、耳でも楽しめるマリオカートに進化しています。
シームレスな世界設計|風景とコースの文脈がつながる工夫
『マリオカート ワールド』最大の特徴は、「世界がつながっている」という設計思想です。
これまでのシリーズでは、個別のコースを選んでレースするスタイルが基本でしたが、本作ではコースとコースが地形ごとに連続しており、1つの巨大なマップを探索・走行できる仕組みになっています。
開発チームはこれを“文脈”として捉え、それぞれのコースがどのような気候・風土・文化圏にあるかを細かく設計。
たとえば、乾いた地域の近くにはサンサンさばくやヘイホーカーニバル、北部には雪山地帯といった具合に、地理とデザインを連動させました。
その地形間をシームレスに移動できるよう、各エリア間には自然な風景の移り変わりが設けられています。
プレイヤーは気づかないうちに新しい地域に入っており、「世界を走っている」感覚を強く味わえる設計です。
視覚的な工夫だけでなく、音楽や環境音も変化することで、よりリアルな世界旅行のような体験が可能になりました。
時間と天候の変化がもたらす新たな体験|24分で1日が巡る
『マリオカート ワールド』のもう一つの革新は、ゲーム内の時間と天候の変化です。
昼から夜、晴天から雨、雪、さらには雷まで――広大なマップを走る中で、リアルタイムに風景が移り変わります。
ゲーム内時間は約24分で1日が一巡する設定。現実よりも早く時間が流れ、プレイヤーは昼夜の変化を頻繁に体験できます。
ただし、すべての時間を均等に描いているわけではありません。
開発チームは「魅せたい時間帯を印象的に切り取る」ことを重視し、夜景や夕暮れの美しさを最大限に引き出すよう時間配分を調整しました。
天候もまた、ランダムではなくレース展開やコースに応じて演出されます。
たとえば、クッパキャッスル周辺では火山の噴火に合わせて天気が急変し、視界が赤く染まるといった動的演出も存在。
これによりレースの臨場感が大幅に増し、走行体験にドラマが生まれます。
環境の変化が、プレイごとに異なる体験を提供してくれる――そんな“走るだけで面白い”世界が、今作では実現されています。
新技「ウォールラン」と「レールスライド」|直線も曲がり角に変える発明
『マリオカート ワールド』では、新しいレースアクションとして「ウォールラン」と「レールスライド」が導入されました。
これは、これまでになかった“直線をどう楽しませるか”という課題への答えです。
開発チームは、地続きの広大なマップをどう走らせるか悩んだ結果、「スケートボードのように街の構造物すべてを遊び場に変える」という発想にたどり着きました。
これが、壁を駆け上がる「ウォールラン」、ガードレールや電線の上を走る「レールスライド」の誕生へとつながります。
これらの技は、スケートやBMXといったエクストリームスポーツにヒントを得たもので、従来のドリフト主体のカーブレースから、「どこを走るかを選ぶ」戦略的な遊びへと進化を遂げました。
特にレールスライドでは、プレイヤーの発想次第で最短ルートを抜けたり、トリックを決めてスピードを稼いだりと、ルート選択の自由度が格段に広がっています。
「ウォールラン」「レールスライド」は、広い世界を自由に走るという今作のコンセプトを象徴するシステムです。
ひとつなぎの世界が生んだ地形設計の工夫|コース間の“違和感”をなくせ
『マリオカート ワールド』最大の特徴は、コースが全て地続きでつながっていること。
これにより、従来の“1レースごとにリセットされる形式”から、“世界を巡る旅”という体験へと進化しました。
しかし、これには大きな壁がありました。それは、バラバラに作られていた過去のコース群を一つの地形に落とし込むという難題です。
例えば「乾いた荒野のサンサンさばく」と「雪に覆われた山岳地帯」をどう自然につなげるか。
こうした無茶とも言える設計を、開発陣は「文脈を大切にする」という手法で解決しました。
間の道に小さなランドマークや気候のグラデーションを配置し、プレイヤーが「いつの間にか景色が変わっていた」と感じるよう工夫したのです。
このアプローチによって、走るたびに景色が変わり、「次は何が現れるんだろう」というワクワク感が生まれました。
道そのものも、ただの接続路ではありません。時には巨大な橋、時にはくねくねした山道となり、それぞれが“世界を構成する一部”としてデザインされています。
NPCが主役に!?「ウシ」参戦が開発に与えた影響|異色のキャラがもたらした新風
『マリオカート ワールド』では、従来のマリオファミリーやクッパ軍団だけでなく、過去シリーズで背景やお邪魔キャラだった存在がドライバーとして登場します。
その代表格が「ウシ」です。
「モーモーカントリー」で見かけたあのウシが、まさかのプレイヤーキャラとしてハンドルを握る…。この斬新なアイデアは、開発チームでも話題を呼びました。
発端は、牧場を舞台にしたコースの試作中に描かれた、「ウシがバイクにまたがる」スケッチ。
これがスタッフの心をつかみ、「これアリかも?」という軽いノリからプロトタイプが作られました。
意外にも動かしてみると違和感が少なく、レースに自然に溶け込む形に。
この成功体験は、さらに他の“おじゃまキャラ”にも波及します。プクプク、サンボ、そしてキリンやラクダまで、レースに参加するNPCキャラが続々追加されました。
さらには、カメックの新アイテムでプレイヤーをNPCに変身させるという“見た目が変わるギミック”にも繋がっていきます。
もはや「マリオたちのカートレース」ではなく、「マリオ世界の住人みんなが参加するお祭り」へと変貌した本作。
この「ウシ参戦」は、その象徴的な一歩だったのです。
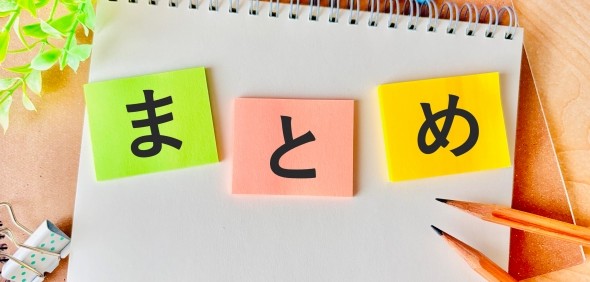
まとめ:『マリオカート ワールド』は“ジャンプアップ”の決意が生んだ進化系
『マリオカート ワールド』は、単なるシリーズの続編ではなく、「9」を名乗らず“ワールド”という名で出発した理由が詰まったタイトルです。
これまでの「1コース単位のレース」から、「世界がつながるシームレスな探索型カートゲーム」へ。
昼夜の移り変わり、地域ごとの気候、直線的な道に挿入されたトリックプレイ、そして“ご当地フード”による衣装チェンジまで。
そのすべてが、“もっと自由に、もっと冒険的に”という開発陣の思いの表れでした。
制作陣は、「マリカーの文法」を残しつつ、遊び方の幅を押し広げることに挑戦し、約8年という歳月のなかでそれを実現。
「9」ではなく「ワールド」とした背景には、ナンバリングを超えた変化と、未来への挑戦が込められていたのです。